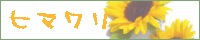


| font-size L M D S |
|
ACT.6 嫉妬
亮は驚いた。滅多に鳴らない携帯が鳴ったからだ。今は移動中で、本番のために少し仮眠を取っていた。もちろん他のメンバーも寝てる。(誰・・?) 知らないアドレスに、亮は悩んだ。とりあえずメールフォルダを開けてみる。『葵です。』というタイトルに、亮は思わず起き上がった。急いでメールを開ける。 〈昨日はありがとうございました。いきなり泣いたりして、びっくりしたでしょ?あの時、何だか妙に安心してつい涙が出ちゃって。それなのにろくにお礼も言わずじまいでごめんなさい。本当にありがとう。昨日は腕を振るえなかったけど、今度は亮くんの好きなもの作るね。あたしにできる些細なお礼。ツアーで大変だと思うけど、頑張ってね。それとあたしの携帯番号も書いておくね。いつでも連絡してくれて大丈夫だから。また戻ってきたら、よかったら寄ってください。〉 亮はメールを見て、何だか嬉しくなった。思わぬ人からのメール。それにいつでも連絡が取れる。それが何だか嬉しかった。早速登録をする。携帯番号を見つめ、少し考える。電話をかけたいが、ここは移動中の車内。運転しているスタッフもいる。何よりこの寝てるメンバーが起きるのが嫌だ。 (向こう着いたら電話しよう。) そう決めた。とりあえず返信しておく。そして亮はまた仮眠を取った。 片付けをしていた葵は着信音に驚いた。 「これかぁ。」 慣れないので、何の音か一瞬分からなかった。手を止め、携帯を取り上げる。メールボックスを早速開く。 「亮くんだっ。」 びっくりしながらもメールを開く。こんなに早く返ってくると思わなかった。 〈お礼なんていいのに。でも葵の手料理ウマイから遠慮なくいただく。それに・・勝手に抱きしめた俺の方がびっくりするやろ。ごめんな。あの時勝手に体が動いて。今丁度移動中やから、向こう着いたら電話するわ。〉 メールはそれで終わっていた。 「電話・・。」 声が聞ける。それが妙に嬉しかった。今日は丁度バイトがない日だ。葵は携帯をエプロンのポケットに入れ、家事に戻った。 到着したメンバーは今夜のステージでリハーサルを始めた。音響をテストする。 「亮、どないしたん?何かソワソワして。」 後ろから見ていた龍二が声をかける。 「別に。」 素っ気無く返す。そんなにソワソワしてるように見えたのだろうか。 「葵ちゃん。」 びくっ。キーボードをいじっていたハズの透がいつの間にか亮の隣にいた。 「やっぱりかぁ。」 透は意地悪く笑った。 「るせっ。」 「何々?透、何か情報掴んでるん?」 龍二も意地悪く聞いてくる。 「別にぃ。俺の勘かな?」 「意地悪せんと教えてや。」 武士までも悪ノリする。 「リハに戻りましょう。」 「えー。」 ブーイングが起こったが、透は教えなかった。亮にとってそれが救いでもあった。今あのメンバーに知られたら、何を言われるか分からない。この気持ちが何なのかまだ分からないのに。 「亮。音合わせるで。」 龍二の言葉に頷く。すると武士が合図を出し、演奏が始まる。B・Dの曲は大半がハードロック。別にロックだけをやってるわけじゃないが、亮には難点があった。 『バラードが歌えない。』 歌えないわけじゃない。でもここでの意味は、聞き手に伝わるような歌い方ができない、ということだ。バラードと言えば、恋や愛の歌。しかし、そんな気持ちを知らずに育った亮には表現できなかった。愛するということが分からない限り、きっと一生歌えない。曲はあっても、亮が歌えるようになるまで、封印していることにした。 『喉、潰しそうに歌うね。』 突然、葵の言葉が過ぎった。 『歌う意味・・難しいね。』 葵との会話が蘇る。歌う意味、自分の存在価値。亮にはリストカットした痕がいくつもある。それを隠すかのようにいつも長袖の衣装だったり、リストバンドのようなものをつけていたりする。 『自分なんていなくても世界は回る。自分一人居なくなったところで、誰も悲しまない。』 そう言ったとき、龍二に殴られたのを覚えている。殴られた痛みより、龍二がその時零した涙の方が痛かった。今まで一人で生きてきた。これからも。でも今は仲間がいる。前よりはそんな思いが薄らいでいる気がする。でもやっぱり亮はどこかでメンバーと壁を作っている。関わらなければ、裏切られることはない。どこかでそんな思いがある。 「っっ。」 亮は頭を抱えて座り込んだ。メンバーはぎょっとした。でもすぐに分かる。いつもの発作だと。時々、亮は頭痛を起こしていた。ひどい時には、倒れてしまう。 「おい、亮。大丈夫かっ!?」 龍二がベースを置いて駆け寄る。他のメンバーも亮に駆け寄った。 「しばらくなかったのにな。」 透が溜息と共に呟く。確かにここしばらくなかった。忙しすぎてそんなことすら忘れていたのかもしれない。 「とりあえず休憩入ろう。お前、しばらく休んで来い。」 龍二に言われ、ガンガン鳴る頭を抑えながら、休憩所へ向かった。 すぐに薬が用意され、亮はそれを飲んだ。 『あんま効かんけどな。』 そう思いながらも、一応飲む。気休めでもいい。この頭痛を少しでも和らげてくれれば。 『亮くん。』 ふと葵の声がした。気のせいだと分かっている。ここに葵がいるわけない。でも、前に葵の家でこうなったことがあった。初めて葵に会った次の日だ。 『亮くん、大丈夫?』 その声であの時、頭痛は不思議と治まった。耳の奥でずっと鳴ってる雑音。葵の澄んだ声が取り払ってくれた。亮は携帯を取り出した。登録したばかりの葵の携帯番号をプッシュする。早く声を聞きたい。 葵は丁度洗濯物を干し終わったころだった。突然鳴り出した携帯に驚く。 「やっぱ慣れないなぁ。」 そう思いながらポケットから携帯を取り出す。ディスプレイには亮の名前が出ていた。 「もしもしっ。」 勢いよくで過ぎた。声が大きかったかもしれない。 『俺・・亮やけど・・。』 「うん。今大丈夫なの?」 『休憩中やから。』 「そう。」 会話が続かない。葵は話題を見つけようと必死になっていた。 しまった。会話する内容を考えてなかった。声が聞きたい一心で電話をかけてしまった。 「あ・・のさ。」 『うん?』 「何してた?」 話題を探りながらそんな事を聞く。 『今ね、丁度洗濯物干し終わったところだよ。今日すごく晴れてて、気持ちいいねぇ。』 葵が笑っているのが、目に浮かぶ。 「そっか。邪魔ちゃうかった?」 『うん。大丈夫だよ。あ、そうだ。亮くん、昨日気分悪そうだったけど、大丈夫?』 思ってもみない気遣いに胸が熱くなる。 「うん。昨日のは・・考え事してたから・・。」 『あぁ。そだったんだ。でも顔色悪かったからね。ちょっと気になったの。』 「ありがと・・。」 小さくお礼を言う。心配してもらえるのがこんなに嬉しいなんて。それに不思議と葵の声を聞いていると落ち着く。頭痛さえも薄らいでくる。 『お礼言われるのも変な感じだけど。ツアー、まだ続くんでしょ??』 「うん。」 『大変だねぇ。栄養あるものちゃんと食べてね。ってお母さんみたいなこと言ってるね、あたし。』 母親の気遣いを知らずに育った亮には、少し新鮮だった。 「うん。大丈夫だよ。響サンがちゃんと考えてくれてる。」 『そっか。響サンがいれば、安心だね。』 会話がまた途切れる。何を話せばいいんだろう。 「あ・・のさ。」 『うん?』 「また時々電話してええ?」 『いいよ。もちろん。』 「ありがと。俺さ、葵の声聞くと、安心すんねん。」 『え?』 亮はハッとした。何を言ってるのだろう。 「あ・・気にせんで。その・・深い意味ないから。」 『う・・うん。』 びっくりしただろうな。突然そんなことを言われたら。 『あたしなんかで良かったら、いつでもいいよ。』 その台詞に亮は舞い上がった。言ってもらえると思ってなかった台詞だからだ。 「ありがと。」 『あ、でもバイトの時間は出れないかもだけど。夜なら大丈夫。』 「うん。電話する前にメールする。」 『OK。それなら大丈夫だね。』 「ありがと。葵の声聞けてよかった。」 頭痛はいつの間にか消えていた。 『こっちこそ。お仕事、頑張ってね。』 「ありがと。んじゃ、そろそろ切るな。」 『うん。』 「じゃあまた。」 『またね。』 亮は名残惜しいと思いながら電話を切った。話せて良かった。葵の声がこんなにも安心するものだと思っていなかった。亮は机に突っ伏した。電話なんて滅多にしないので、妙に緊張した。相手が葵だから余計に。声を聞けて嬉しいのに、電話を持つ手が震えていた。何だろう。この気持ち。何だろう。この感じ。亮は全く分からなかった。 葵は上機嫌で電話を切った。 『葵の声聞けて良かった。』 亮の言葉が反芻する。顔が真っ赤になる。そんなこと言われた事ないので、恥ずかしい。でもまた電話をかけてくれる。それが妙に嬉しかった。 亮が医務室に行って休憩している間に、透はメンバーを集めた。 「どした?」 龍二に聞かれ、話を切り出す。 「亮のことなんやけど。一応皆の耳に入れておいた方がいいと思って。」 真剣な顔に全員が聞き入る。 「亮?さっきの頭痛?」 武士の問いに、首を振る。 「その事じゃなくて。昨日の1件で分かったこと。」 「昨日?」 今度は慎吾が聞き返す。そうだ、と頷いて透が続ける。 「葵ちゃんが1人だって聞いたとき、あいつ真っ先に飛び出してったやろ?その前から何となく分かってたけど・・。あいつ・・葵ちゃんのこと好きなんちゃうかなって。」 「え?」 「亮が?」 慎吾と武士が驚く。龍二は黙って聞いていた。 「うん。普段の亮ならあんな行動せんやろ?」 「言われてみれば・・確かに。」 「それで昨日聞いてみたんや。亮自身に。」 「葵ちゃんのこと?」 「そう。どう思ってるかってね。」 「何て?」 続きを催促する。 「『分からん』って。」 「は?」 思わぬ返答にメンバーは呆れた。 「あいつ・・愛するって感情が乏しいと言うか・・どんなものか分かってない。だから『分からん』て答えた。」 透の言葉に納得する。 「でもあいつ、葵ちゃんを抱きしめたって言ってた。」 「ええ!?」 「亮が!?」 メンバーは驚いた。女嫌いを知ってるからだ。葵が初めから大丈夫だったとはいえ、まさか抱擁までするとは。 「本人は何でか分からんって言ってる。でも亮は葵ちゃんの事を好きなんだと思う。」 「そら・・そうやんな・・。」 「気にしてるなってのは思ってたけど、そこまでとは。」 武士と慎吾が交代するように言う。 「もしかしたらこの機会に女嫌いが克服されるかもしれんし。・・・俺、葵ちゃんに賭けてみようと思ってる。」 透の言葉にメンバーは首を傾げた。 「賭ける?」 「そう。葵ちゃんがどう受け止めるかは分からんけど・・。でも葵ちゃんなら亮を変えられるかもしれん。」 透が言うことはもっともなように思えた。 「あいつに・・亮に・・愛するって言う感情を教えてやりたい。」 透は机の上に置いてあった両手の拳を握った。 「透の気持ちは分かった。俺たちはどうすればいい?」 黙って聞いていた龍二が問う。 「何もしなくていい。」 「え?」 思わぬ返答に驚く。 「何もって・・。」 「ただ普通にしてればいいよ。でも亮がもし悩んだりしてたら、アドバイスしてやってくれ。ただそれだけでいい。」 透の言葉の意味を掴んだメンバーは頷いた。 「でも問題は葵ちゃんやんねぇ。」 慎吾が眉根を寄せる。 「あぁ。それなら大丈夫やと思うで。」 妙に自信ありげに言う龍二。 「何で?」 「香織に聞いたけど、葵ちゃんも亮のことちょっと気になってるらしい。」 「へー。じゃあうまく行けば両想い?」 慎吾が楽しそうに言う。 「そうやろうけど。葵ちゃんも恋愛下手っぽいから、あんま俺らが突付くのもどうかと思うけどな。」 龍二は持っていたタバコに火をつけた。 「葵ちゃん・・狙ってたのになぁ・・。」 武士がしょんぼりと言う。 「こればっかりは仕方ないやろ。」 慎吾は武士の肩を優しく叩いた。 「んだな。諦めっかぁ。」 「早。」 「俺様にはもっといい女が・・。」 「はいはい。」 慎吾は軽く流した。 「とにかく・・そういうことやから、皆よろしくな。」 透が締める。メンバーは快く頷いた。 葵の声を聞いたおかげか知らないが、亮はその日それから頭痛が起きなかった。ライヴも大成功を収めた。ライヴが終わるとホテルに戻った。ホテルでメンバーは各々の部屋でまた明日のライヴの練習や気晴らしなどをしていた。亮はギターを鳴らしていた。ふと視界に携帯が目に入る。 『電話・・してみようかな・・。』 時計に目をやる。午後11時。きっとまだ起きている時間。とりあえずギターを傍らに置き、携帯を取った。慣れないメールを打つ。 〈まだ起きてる?〉 すぐに返信が返ってくる。 《起きてるよ。どしたの?》 〈電話してもいい?〉 《いいよ、もちろん。》 快い返事が返ってきて、亮は安心した。早速電話をかける。コール2,3回で葵が出た。 『もしもし?』 「あ・・俺・・やけど・・。」 『うん。ライヴお疲れ様。』 「ありがと・・。」 葵の声を聞いて何故か安心した。昼間にも聞いたが、その何倍も落ち着く気がする。 『今は?何してるの?』 「あ・・ホテルの部屋で・・ギター弾いてた。」 『そなんだ。』 「葵は・・?」 『丁度お風呂から上がったとこ。今自分の部屋だよ。』 「そっか。タイミング良かったな。」 『だね。』 葵の笑い声。聞いてて心地いい。他愛のない話。他人とあまり話さない亮だったが、葵となら何でも話せる気がした。 ツアー中、亮は葵と毎日電話した。少しの合間を見ては、メールをした。他愛のない会話。こんなことをするのは初めてだった。 「亮くん、そんなに必死に誰とメールしてるんですかぁ?」 武士が意地悪く聞く。 「お前に関係ない。」 「冷たいなぁ。あ・・もしかして・・葵ちゃん?」 少し動揺したのが、武士にも分かった。 「ふーん。なるほどね。」 「るせーよ。あっち行け。」 「へぃへぃ。お邪魔虫はどっか行きますよ。」 武士はあまり突っ込まないように、他のメンバーがいるところに逃げる。 「やっぱ葵ちゃんやったわ、相手。」 武士は報告した。 「なら・・うまく行ってるってことか?」 龍二はタバコの火を点けながら問う。 「あんなに四六時中携帯いじってる亮、初めて見た。」 慎吾が感想を述べる。 「今のとこ順調みたいやな。あんま波風立てんようにせんとな。」 透の言葉に一同頷いた。 双子は面白くなかった。いつもリビングやキッチンに行けば葵が居たのに最近では自室に篭っていた。例え居ても亮から一度メールが来ると、自室に戻ってしまう。最近そればっかりだ。 「何か・・携帯プレゼントしたの間違ったかなぁ。」 直人が呟く。 「かもな。」 快人が頷く。 「亮さんのアドレス教えたのが間違いかなぁ。」 「かもな。」 直人の呟きに同じように返す。 「快人はいいの?」 「何が?」 「葵ちゃん、いつもならこの番組一緒に見るのに。」 「しょうがないだろ。こればっかりは。」 快人は諦めムードだった。直人はしかめっ面でテレビを見た。 夏休みはとうに終わり、快人と直人は学校が始まっていた。 「葵ちゃん、ここ教えて。」 いつものように勉強を教えてもらおうとキッチンに直人がやって来る。 「あぁ、これはね・・。」 葵はいつものように教えていた。 「そっか。なるほど。」 その時葵の携帯が鳴った。電話じゃなくてメールだった。葵はすぐに返信をする。 「・・今の亮さん?」 念のために聞く。 「あぁ、うん。そだよ。」 あっけらかんと答えられ、直人は複雑だった。 「で、これはね。」 葵は説明を続けたが、直人は素直に聞けなかった。どこかでモヤモヤしている。 「葵ちゃんは・・亮さんのこと好きなの?」 「え?」 突然の問いに葵は戸惑った。 「何・・急に?」 「答えてよ。」 「好き・・だけど。友達の好き、かな?」 葵の答えにも、少しモヤモヤした。もしかして気づいていないだけなのだろうか?複雑な思いは変わらない。 「どしたの?急に。」 「何でもないよ。」 直人はそう言うと片付けをし始めた。 「もう・・いいの?」 まだ教え終わっていない葵が問うと、直人が頷く。 「ありがとう。もういいよ。」 小さくそう言うと自室に戻った。 翌日。葵は一通りの家事を終わらせ、バイトに向かおうとした時、メールが入ってくる。見ると直人だった。 〈ごめん。体操服忘れちゃって、どうしても次いるから届けてもらえないかなぁ?無理ならいいんだけど。〉 「珍しいな。直人が忘れ物するなんて。」 そう思いながら、葵は直人の部屋に入り、体操服の入っている袋を持って部屋を出た。バイト行く前に届けなければいけないので、少し早めに出ることにした。 「葵ちゃん、こっちこっち。」 学校に着くと、閉められた門の向こう側に直人がいた。 「はい、体操服。」 持ってきた袋を手渡す。 「ありがとう。体操服忘れると減点なっちゃうからさぁ。」 「そっか。でも珍しいね。直人が忘れ物するなんて。」 「今日寝ぼけてて体操服要らないって思っちゃったんだよね。」 苦笑しながら答える。 「そお。あ、着替えなきゃでしょ。早く行った方がいいんじゃない?」 「うん。ありがとぉ。」 そう言って直人は去っていった。葵もバイト先へ急いだ。 「直人。今葵来てた?」 更衣室へ向かう途中、快人に会う。 「うん。体操服忘れたから持ってきてもらった。」 「そか。」 「快人も早く着替えなきゃ。」 「あぁ。」 同じクラスの2人は更衣室へ向かった。 それから3日後。快人が珍しく熱を出した。 「うわぁ。38度6分。」 体温計を見た直人が驚く。快人は辛そうに息をしている。 「直人は学校行かなきゃ、遅刻だよ。」 氷枕と濡れたタオルを手に葵が入ってくる。 「うん・・。」 「心配なのは分かるけど、ちゃんとあたしがついてるから大丈夫だよ。」 葵は快人の頭を起こし、氷枕に変え、額に濡れタオルを乗せた。 「多分、風邪だろうし。ちゃんと看病するから。」 葵は直人を送り出した。その後、葵はバイトに休みの電話を入れた。 「快人が熱、出しちゃって。」 『そうか。それは仕方ないな。今日はゆっくり看病したげて。』 店長は快く了承してくれた。それもこれも葵たちの事情をよく知っているからだ。 「ありがとうございます。」 葵はお礼を言って電話を切った。それから家事をこなしながら、快人の看病をした。 「お粥、作ったよ。」 お昼頃、快人の部屋に持ってくる。 「いらにゃい。」 小さく呟く。 「何か食べなきゃダメよ。お薬飲めないでしょ。」 葵は持ってきたお盆を部屋の真中にある小さい机の上に置いた。 「快人の好きな卵とネギ入れたよ。」 小さな鍋に入っているものを、持ってきた茶碗に移す。それを机の上に置き、快人の方に机を寄せる。 「ほら、起きて。」 無理やりに起こす。快人は熱のせいでボーっとしていた。 「食べさせてあげようか?」 「自分で食うよ。ガキじゃあるまいし。」 葵からお茶碗とスプーンを受け取り、少し冷ましながら口に運ぶ。お粥を作っている間に計った体温計を見て、葵は少し安心した。ほんの少しだが熱が下がっていた。 「風邪?」 本人に聞いてみる。 「さぁ。でも俺、咳とか全然出てなかったし。昨日も普通に風呂入ってすぐ寝たし。」 「疲れかなぁ?」 夏休み、休む暇なく働いたのだ。今疲れが出てもおかしくはない。 「疲れとかなら・・直人も同じくらい働いたんだから、そのうち直も出るんじゃねぇの?」 「あぁ。かもねぇ。」 快人の言葉に頷く。 「よし。今日は栄養あるもの作って食べさせようっと。」 「俺・・あんま食欲ないからな。」 お粥を食べながら言う。 「熱が下がれば食欲も出てくるって。快人には、特別に作ったげるからね。」 「へぃ。」 葵は快人が食べ終わった食器を片付け、自分も昼食を取り、食後のコーヒーを入れていた。その時携帯が鳴った。 「メールだ。」 ようやく携帯の扱いに慣れてきた。毎日亮とメールをしている賜物だ。 〈今電話できる?〉 《もちろん、大丈夫だよ。》 そう返すとすぐに電話が鳴った。 「もしもし?」 『もしもし。大丈夫?』 「うん。あたしはね。」 『え?』 「快人が熱出しちゃったの。」 『大丈夫なん?』 「うん。多分夏の疲れだと思うんだけど。」 『そっか。あいつらも結構仕事してたしな。』 「そうなの。今度直人が倒れないか心配で。」 『せやな。』 「亮くんも、気をつけてね。」 『え?』 「無理しないでね。疲れたときはゆっくり休まないと、倒れちゃうよ?」 『せやな。』 亮は口元が少し緩んだ気がした。 午前中の授業で帰ってきた直人はリビングに入ろうとして止まった。ドアの向こうで葵が笑っている。相手はきっと亮。毎日のように電話やメールをしている。何だか胸にぽっかり穴が開いたみたいだ。直人はリビングのドアノブにかけていた手をそっと離し、自室へ向かった。 着替えてから快人の様子を見に来る。 「快。大丈夫?」 「んぁ。直。もう帰ってたんか。」 「うん。今日午前中授業だったから。」 「・・そいやそか・・。」 直人は快人のベッドの近くに座った。 「どした?」 赤い顔をした快人が直人に問う。 「別に・・。」 「別にって顔してないぞ。何かあった?」 直人は胸のモヤモヤを快人に話した。 「何か・・葵ちゃんが遠くに行っちゃいそうで。」 「亮さんと仲良いから?」 快人の問いに頷く。 「そりゃ・・亮さんはいい人だし、葵ちゃんが誰を好きになろうと俺には関係ないかもしれないけどさ。」 「何だか気に入らないと。」 その問いにも頷く。 「お前は根っからの甘えん坊だからな。」 「何だよそれ。」 快人の皮肉にムッとする。 「でも・・俺もその気持ち分かるよ。」 快人の思わぬ言葉に直人は顔を上げた。 「俺も・・ちょっと寂しい気がする。」 「快・・。」 「親父たち死んでから葵はずっと俺たちの傍に居てくれたからな。余計かも。」 「そうだね。」 「双子揃ってシスコンとはな・・。」 快人の言葉に直人が笑う。 「そうだね。」 しばらく快人と話してリビングに下りると、葵は洗濯物を取り込み、たたんでいた。 「あれ?直人、もう帰ってたんだ。」 「うん。」 「いつもリビング寄ってから上に上がるのに珍しい。」 葵はそう言って笑った。亮と電話しているのを見てるのが嫌だった、なんて言えない。直人は冷蔵庫からジュースを取り出し、コップに注ぐ。何ともなしに葵を見る。いつもと変わらない。 「どうかした?」 視線に気づいた葵が問う。何でもないと首を振り、直人はコップを持って葵の近くのソファに座った。 「はい、これ直人のね。」 たたみ終わった服を渡す。 「ありがと。」 「どういたしまして。」 笑顔で言われる。 「ねぇ、葵ちゃん。」 「ん?」 無意識に葵を呼んでいた。急いで話題を見つける。 「・・今日の夕飯何?」 「うーん。栄養がいっぱいあるもので献立考えてるんだけど、まだ決まってない。」 苦笑しながら答える。 「直人、何か食べたいものあるの?」 「んー・・あ、肉じゃが。」 「肉じゃが?和食がいいの?」 「うん。」 「分かった。じゃあ今日は和食で作るね。」 「うん。」 「そうだ。松木さんに連絡しなきゃ。」 「ん?何で?」 「快、熱あるって。」 「それならもうしたよ。」 「あれ?そなの?」 「うん。俺が学校行くときにしといた。今日はレッスンだから、ゆっくり休めって。」 「そっか。ありがとね。すっかり忘れてた。」 「だろうと思った。葵ちゃん、時々どっか抜けてるよね。」 「そうなの。ボケボケなのよ。って直?」 ノリツッコミで答える。 「それを言うのはこの口かぁ。」 葵は直人のほっぺをつまんだ。全然痛くない。 「あはは。かわいいって意味だよ。」 フォローしておく。 「ホントにぃ?」 「ホント。」 「なら許そう。」 葵とこうしてじゃれあってるだけで少し気持ちが落ち着いた気がした。 2日後、快人は完全復活したので、また直人と2人で仕事に励む。事務所で打ち合わせをして、帰ろうとした時。 「いたいた。快、直。」 呼ばれ、2人が振り返るとそこには透がいた。 「あれ?透さん。ツアー中じゃ。」 直人が気づいて問う。 「今日はこっちで仕事があったから、1回戻ってきたんや。2人、ちょっとだけ時間ある?」 2人は不思議に思いながら頷いた。 3人は移動して、事務所の中の誰も使っていない会議室へ来た。 「ごめんね。呼び止めたりして。」 「いえ。何ですか?話って。」 快人が催促する。 「亮と葵ちゃんのことなんだけど。」 そう言われ、微妙にドキッとする。 「どうかしたんですか?」 動揺しているのを隠しながら直人が聞く。 「2人、よくメールや電話してるみたいなんやけど。どうなんかと思って。」 透の言ってる意味がよく分からない。透は言葉を付け足した。 「葵ちゃんは亮と電話してる時、どんな顔してる?」 どんな顔しているか、2人は思い出していた。 「楽しそうです・・。」 直人が答える。 「よく笑ってるし。」 快人も答える。 「そか。」 そう言って透はホッとしたような笑みを浮かべる。 「どうかしたんですか?」 直人は透の表情の意味が分からなかった。 「俺さ、葵ちゃんが亮の心を解き放つ存在だと思うんだ。」 「え?」 「亮は、2人も知ってる通り、女嫌い。それに加えて自分は居ても居なくてもいい価値のない存在だと思ってる。」 透の言葉に驚愕した。そんな話は初めて知った。 「あいつが女嫌いになったのは、母親に捨てられたからなんだ。」 「え?」 「必ず迎えに来るとそう言い残して、亮を施設に預けた。」 亮の知らない過去を聞かされ、2人は戸惑った。 「それかららしい。人間、特に女の人は裏切る生き物。自分を愛してくれる人なんて居ない。居なくても世界は回る。そう思い込んでる。」 一息吐いて透は続けた。 「あいつの衣装が長袖が多かったり、普段左腕にリストバンドしてる訳、知ってる?」 その問いに2人は首を横に振った。 「リストカットの痕があるんだ。」 「!?」 透の答えに2人は言葉を失った。 「自分は価値のない人間だから、死んだほうがいいんだって、何度も自分の腕を傷つけた。その度に俺や龍二が止めに入った。」 双子は青ざめた顔で聞いていた。 「ごめんな。こんな話して。でも・・2人には分かって欲しくて。」 その言葉の意味を理解できない。 「葵ちゃんと話してる亮はどこか嬉しそうで、『死にたい』と口にしてたあの頃の亮じゃない。俺は・・葵ちゃんなら亮の心を開けるんじゃないかって思ってる。」 何となく事情が掴めてきた。最初に言った透の言葉の意味を理解した。 「2人は葵ちゃんを取られた気がして、気持ちがいいもんじゃないかもしれないけど・・。協力してやって欲しい。」 「協力って・・俺・・できません。」 直人が思わぬ言葉を吐く。 「え?」 「俺・・嫌なんです。亮さんがいい人だってことも分かってますし、話を聞いて亮さんの事も分かりました。けど・・。」 「けど?」 透は続きを催促した。 「亮さんと楽しく話してる葵ちゃんを見て、何か・・こう・・モヤモヤするんです。」 「モヤモヤ?」 「何かすっきりしないと言うか・・。だから・・協力なんて・・もっとできません。」 「快人は?」 直人の言い分を聞いて、今度は快人に話を振る。 「俺も・・正直嫌です・・。」 「直人と同じ?」 透の問いかけに頷く。 「そっか。」 透は溜息を吐いた。 「すいません・・。」 呟くように2人は謝った。 「2人の気持ちも分からんでもないよ。」 透の思わぬ言葉に2人は俯いていた顔を上げた。 「葵ちゃんが親代わりだったんやろ?ずっと傍にいる存在だった。でも急に亮に取られた気がして、何かモヤモヤする。違う?」 2人は首を横に振った。 「前に言ってくれたよな?葵ちゃんは自慢の姉貴だって。16で親亡くして、それからずっと自分たちの面倒見てくれたって。倒れるまでバイトしまくって、それで自分たちも働こうと思ったって。」 以前、透たちにそんな話をしたことを思い出す。芸能界に入ったのは、少しでも葵を楽にさせたかったからだと。 「ぶっ倒れるまでバイト尽くしで、それで高校行って勉強して・・葵ちゃん、恋する暇なかったんちゃう?」 言われてハッとした。 「恋だけじゃない。きっとしたい事もずっと我慢してたと思うよ。」 したくてもできなかった。状況が許さなかった。時間が空けばバイトや家事に明け暮れてた。もちろん家事は自分たちも手伝っていたが、バイトまでは手伝えなかった。だからこそ芸能界に入ったのだ。 「自分を犠牲にして、ここまで育ててくれた葵ちゃんに感謝してるやろ?」 その言葉に頷いた。 「分かりました・・。俺・・協力します。」 快人が先に口を開く。直人も頷く。 「俺も・・。」 「ありがと。俺・・亮にも葵ちゃんにも幸せになって欲しいんだ。」 そう言って透は微笑んだ。双子も頷いて笑った。 2人がリビングに入ると、美味しそうな匂いが漂ってきた。 「おかえりー。」 食事の準備をしていた葵が笑顔で迎える。 「今日は2人の好きなハンバーグだよぉ。」 食器を並べながら、葵が説明する。 「うまそー。」 「手洗ってきな。」 つまみ食いしようとした快人の手をペチンと叩きながら言う。2人は言われた通り手を洗う。そして一緒に食事を取る。 「快人、大丈夫だった?」 病み上がりに仕事に行った快人を心配する。 「大丈夫だよ。もう熱下がったし。」 「油断してたらまた熱出るよ。」 「気ぃつけます。」 素直に返事をする。 「直人も気をつけてね。2人とも無理しないで。」 「大丈夫だよ。ありがとう。」 直人は心配されたことが嬉かった。葵が亮を好きでも、自分たちの姉であることには変わりはない。この関係は終わることはない。そう思うと何だか妙に安心した。 ゆっくり楽しんだ食事も終わり、食器を片付ける葵。 「葵ちゃん。」 不意に直人に呼ばれ、振り返る。 「ん?どしたの?」 「ごめんね。」 「え?」 急に謝られたので、訳が分からない。 「俺も・・ごめん。」 「何で2人が謝るの?」 理由が分からないので、葵は混乱している。2人は顔を見合わせて笑った。 「ちょっと何笑ってるのよ。」 「何でもない。」 直人が言う。 「何でもねーよ。ご馳走様。」 「ご馳走様ぁ。」 2人は逃げるように自室へ戻って行った。 「何なの・・一体。」 葵だけ訳が分からなかった。 |