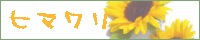


| font-size L M D S |
|
ACT.10 想い
今日はレコーディング。意外と早く音が固まったので、早速音入れをしてみる。「歌えるんかな・・亮。」 明るい曲調を歌うのは初めてかもしれない。メンバーは不安そうにブースの外から見守った。 そして歌いだす亮。一同、呆然とした。 「あ・・あれ?」 「え・・。」 いつもと明らかに違う歌い方。以前から歌い方が変わってきたのは、感づいていたが、それまでとは違う誰も知らない亮がそこにいた。 「・・あいつ・・練習したんかな?」 武士が呟く。メロディを覚えるために多少は練習するだろうが、何だかやっぱり違和感は否めない。 「うわぁ。めっちゃ違和感。」 慎吾が思わず呟く。いつもの亮と180度違う。 「俺も同感。」 龍二が頷く。 「でも正直・・歌えるとは思わんかったな。」 作曲者である透が呟いた。この曲はある意味賭けだった。亮の気持ちが変化している今だからこそ、歌ってみて欲しいと思った。だが正直歌えるとは思わなかった。 歌っている亮の表情はどこか穏やかで、今までに見たこともない表情だった。 その頃由香は携帯と睨めっこしていた。 「由香、何やってん・・。」 呆れた雅紀が問う。 「うー・・。こないだのこと亮に謝ろうと思ってんねんけど・・。」 「さっさと謝ったらええやん。」 「そんな簡単に謝れんわ。」 「何で?」 「亮・・絶対呆れてる・・。」 「大丈夫やって。」 「・・そんな保障どこにあんの?」 由香にキッと睨まれる。 「大体、亮はあれくらい何とも思ってへんて。」 「その方が嫌や・・。」 「どっちやねん。」 「ほっといて。」 「訳分からん。」 雅紀は呆れて溜息を吐いた。 『・・よし・・かけるぞ・・。』 由香は心を決め、いざ通話ボタンを押す。コール音が緊張を増幅させる。今の時間、仕事かもしれない。出なくて当たり前かと切ろうとした時だった。 『はい?』 「あ、も・・もしもし?・・由香ですけど・・。」 『あぁ。どした?』 普通に聞かれ戸惑う。声のトーンからして、別に嫌がってる訳じゃない様だ。 「こないだのこと・・謝りたくて・・。」 『あぁ、別に気にしてへんかったのに。』 「でも・・しつこくして・・ごめんなさい・・。もう・・しないから。」 『そうしてくれると助かる。』 「・・ほんま・・ごめんなさい。」 『もうええよ。』 優しい言葉にまた泣きたくなる。 「一つだけ・・ええかな・・?」 『ん?』 「メールの相手って・・亮の好きな人?」 意を決して聞いてみる。どんな答えが返ってきても覚悟はできてる。 『・・せや。俺が好きな人。向こうはどう思ってるかは知らんけど。』 「・・そう・・。」 正直に答えられ、由香はそれ以上何も言えなかった。 「ごめんなぁ。変なこと聞いて。正直に言うてくれてありがと。仕事邪魔して・・ごめん。」 『ええよ。今休憩中やし。』 「そっか・・。また暇なとき連絡して、お兄ちゃんと3人でご飯食べに行こうな。」 『おう。』 「ありがとう。じゃあ・・またね・・。」 『またな。』 そう言うと電話は切れた。由香は呆然としていた。亮に好きな人ができた。素直に喜べない。 『どうして・・うちやなかったんやろ・・。』 ずっと亮を見てきた。亮のことは何でも知ってる。だけど亮は、見てくれなかった。こっちを向いてくれなかった。涙がまた溢れ出す。亮を変えたのは、自分じゃなくて、亮の好きな人。亮を変えることすらできず、ただ見守っているだけの自分に亮が向いてくれるはずがない。好きなのに・・・・こんなに好きなのに。 状況を察した雅紀は、由香の隣に座り、由香の肩を優しく抱いた。 数日後。事務所に立ち寄った亮は、快人と直人に会った。 「あ、丁度良かった。」 「?」 「これさ、葵に渡して欲しいんやけど。」 そう言って渡されたのは1枚のCDだった。 「CD・・ですか?」 「新曲のデモなんや。葵に聞かせるって約束したから、多分渡したら分かると思う。」 「なるほど。あ、俺たちも聞いていいっすか?」 興味が沸いた快人が問うと、亮は頷いた。 「あぁ。ええで。」 「やった。」 「んじゃ頼むな。」 そう言って亮は2人の前を去った。 双子は帰ってきて早々、葵にCDを渡した。 「何?」 「亮さんに頼まれたの。葵ちゃんに渡してって。」 「新曲のデモとか言ってた。」 「あぁ!ありがと。」 2人の説明でこの間言っていた曲だと気づく。早速3人はリビングにあるステレオで聞こうと集まっていた。CDケースを開けると、CDに手書きで曲名らしきものが書いてあった。 「『Love Letter』ってタイトルみたいね。」 葵はそう言いながら、CDをステレオにセットした。流れ出す前奏。曲調に3人は驚いた。いつものハードロックではなく、ポップだった。 「初めてじゃない?こんな曲調。」 直人が言い、葵と快人が頷く。曲調に驚き、亮の歌い方に更に驚いた。 「全然違うっ!?」 「声も何か違う気がする・・。」 直人と快人が呟く中、葵は驚いて声が出なかった。こんな明るい曲を歌うとは思わなかった。あの喉を痛めそうな歌い方ではなかった。 「声・・綺麗・・。」 葵はやっと声を出した。心からそう思った。双子も頷く。 葵は気づいていないようだったが、双子は気がついた。あの曲の歌詞は、葵のことを書いていると。 『やっぱり亮さんは葵のこと・・。』 快人は直人と目を合わせた。直人も同じことを考えているようだ。複雑な反面、何だか嬉しい。 「葵って、亮くんのことどう思ってるのさ?」 突然の美佳の問いに、葵は飲んでいたコーヒーを噴出しそうになる。 「なっ!何を突然!」 「好きなの?」 「す・・好き・・だけど・・。」 素直になった葵に美佳はちょっと驚く。 「でも・・亮くんに迷惑がかかる・・。」 葵の言葉に美佳は溜息を漏らした。 「あのねぇ・・そんなこと言ってると一生恋なんてできないよ?」 「う・・うん・・。」 分かってはいる。だけど、相手の亮は人気バンドのヴォーカリストなのだ。美佳は溜息を吐いた。 「葵の気持ちも分かるよ。だけどそんなんじゃいつまで経っても前へは進めないよ?」 「うん・・。」 葵は恋愛下手なことくらい、美佳も知っている。あまり言い過ぎても葵は引いたままだろう。 『どうするかなぁ・・。』 美佳は何としても2人をくっつけたかった。2人には幸せになって欲しかった。 その頃、武士と亮はスタジオの休憩所で休んでいた。 「なぁ、亮。」 「ん?」 「あの『Love Letter』ってさ、葵ちゃんのこと想って書いたんやろ?」 武士の一言に亮は動揺した。 「・・ま・・まぁな・・。」 「やっぱ亮は葵ちゃんのこと好きなん?」 「何をイキナリ。」 武士の突然の問いに亮は戸惑った。 「でも少なくとも亮は葵ちゃんのこと、好きなんやろ?」 武士の問いに、亮は少しの間を空け、こくんと頷いた。 「そっか。ならさ、気持ち伝えようとか・・思わんの?」 「・・・。」 「焦る必要はないと思うけどさ、気持ちはやっぱ伝えた方がええと思うで。せっかく亮が人を好きになれたんやからな。」 「・・武士。」 「ん?」 「俺さ・・怖いんやと思う。」 「怖い?」 突然話し始めた亮に武士は耳を傾けた。 「俺がホンマに人を好きになれるなんて思ってへんかったし。俺は・・葵んこと好きやけど、向こうはどう思ってんねやろって・・。そればっか考えて・・。」 亮の言葉に武士は何処か安心した。 「それが普通や。」 武士はポンッと亮の肩を叩いた。 「でもな、何にしても自分から動かんかったら、何も変わらん。それくらい分かってるかも知れへんけど。葵ちゃんも亮の言葉待っとると思うで?」 「え?どういう意味?」 武士の言葉を思わず聞き返す。 「それは葵ちゃんに気持ち伝えたら分かるこっちゃ。」 意地悪く返される。 「・・・言えるならとっくに言ってるよ・・。」 亮の呟きが聞こえ、武士は励ましの意味を込め、優しく肩を叩いた。 それからツアーに出たB・Dは忙しい日々を送っていた。葵とは相変わらずメールのやり取りだけだったが、亮はそれでも十分だった。葵の言葉だけで、次のライヴも頑張れる気がした。とは言ってもやはり『会いたい』気持ちはずっとあった。それを表に出ないように必死に抑えた。ライヴに専念して忘れようとした。 葵も会いたい気持ちを抑え続けた。無理に忘れるのではなく、考えないようにした。 そしてまた夏がやってきた。 蝉の声が鳴り止まぬ8月半ば。お休みを取った双子と葵は両親の墓参りに来ていた。今年こそはちゃんと3人で来られたので、墓掃除をした。とは言っても月に一度は葵が墓参りに訪れているので、そんなに掃除をしなくても良かった。 葵はふと去年の出来事を思い出した。亮が突然現れ、抱きしめてくれたことを。あの時は本当に驚いたけど、亮の優しさが伝わって、素直に泣けた。あれからもう一年が経ったのかと妙に感慨深くなってしまう。 「葵ちゃん?」 ボーっとしていると直人に声をかけられた。 「あ・・ごめん。何?」 「そろそろ家に帰ろうって。」 「あ、うん。そうだね。」 3人は仲良く家路に着いた。 家に着いたのは、夕方だった。 「今日晩御飯どうするの?」 「んー。何か食べたいものある?」 「てか今日は葵の誕生日でもあるんだからさ。葵が決めていいんだぜ?外食でも行くか?」 快人の意見に直人が賛成する。 「それいいね。葵ちゃんも疲れただろうし。」 「外食かぁ・・。」 「何か食べたい物ってある?」 直人がそう聞いたときに、電話が鳴った。葵が出ようとしたのを直人が代わりに出る。 「はい。日向です。」 『おー。俺。龍二やけど・・。』 「あー、龍二さん。どうしたんです?」 『・・お前は・・直か?』 「はい。そうですよ。」 声も快人と直人はそっくりなので、龍二は迷ったらしい。 『あのさー、晩飯とか決まってる?』 「いえ。今から外食に行こうかって話してたんです。」 『ならちょうどいいや。俺んちで一緒に食おうで。』 「え?」 『今日久しぶりにこっちに戻ってきたからよ。3人で俺んち来い。』 「わー。じゃあお言葉に甘えさせてもらいます。」 『おう。待ってるよ。』 直人は電話を切ると、2人に電話内容を伝えた。 「行く返事しちゃった。」 えへへと笑う直人に2人は呆れたが、龍二の言葉に甘えて行くことにした。 直人は行く道すがら快人にこっそり耳打ちをした。そして葵を先頭に龍二宅へ入る。そしてリビングのドアを開けると、一気にクラッカーが鳴らされた。 「「「ハッピーバースデー。」」」 葵は鳴らされたクラッカーに驚きつつも、去年と同じく騙された自分に思わず笑顔になる。 「びっくりした。」 見渡すとB・Dメンバーが揃っており、香織が1歳になった龍哉を抱き、美佳もクラッカーを手にしていた。 「ホントにびっくりしちゃった。」 それしか言葉が出ない。去年に引き続き騙されるとは・・。 「ありがとうございます。何て言ったらいいか・・。」 「硬い事はいいから、座って。お腹空いたでしょ。」 香織が座るように促したので、言われたとおりに席に着く。プレゼントを渡され、香織や美佳が作った料理に舌鼓を打つ。 「今年はちゃんと忘れなかったみたいね?」 美佳は隣に居た双子に意地悪く言う。 「お、俺たちだって忘れたくて忘れてた訳じゃ・・。」 「分かってるって。でも日付感覚忘れるくらい忙しいってことよね。」 美佳の言葉に双子はどう切り替えしていいのか悩んだ。 「まったく。松木さんももうちょっとしっかりしてくれたらねぇ。」 元はと言えばおっちょこちょいのマネージャー松木がスケジュールをちゃんと確認してなかったからだ。もちろん双子にも多少の責任はあるが。 「だから今年は最初から空けるように手帳にマークしてたみたい。」 直人は笑いながら言った。前回の責任を感じたのか、今年はちゃんとスケジュールを入れないようにしていた。 「売れっ子になると大変やねぇ。」 「何を他人事みたいに言ってるんですか。武士さん。」 快人が呆れたように言う。BLACK DRAGONだって休みがないほど忙しい売れっ子のロックバンドなのだ。 「そういや今日新曲発売日だっけ?」 「さっすが美佳ちゃん。ファンって言うだけあるなぁ。」 「茶化さないで。デモ聞かせてもらったけど、どういう心境の変化?」 「んー。元は透が持ってきた曲なんやけど、一番変わったのはやっぱあいつかな?」 武士は亮の方に目線を送った。 「亮くん?」 「あいつが『やってみたい』って言うたんや。それまで絶対そんなこと言わんかったのに。あいつの中で何か変わろうとしてるんかもな。」 美佳は武士の言葉を聞きながら、亮を見つめた。 葵は火照った体を冷やすためにベランダに出た。流石人気のあるバンドのリーダーだ。マンションは最上階で、下を見下ろしても暗くて見えないくらい高い。遠くを見つめると綺麗な夜景が一望できる。 「くしゅっ。」 「いくら夏でも風邪引くで。」 「亮くん・・。」 亮はそっと上着を葵に着せた。 「ありがと。」 亮も葵と一緒に夜景を眺める。 「何か・・久しぶりだね。」 「せやな。」 ゆったりと流れる時間。亮はずっと隣に居たいと思った。それは葵も同じで、2人は思いが通じ合ってるような気がした。 『葵ちゃんも亮の言葉待ってると思うで?』 ふと武士の言葉が浮かんだ。 『俺の言葉を待ってるって何や・・?』 何故武士がそんなことを言うのか分からない。大体何て言えばいいのか分からない。 『どうしたらええんや・・。』 「・・だね。」 「え?」 「相変わらず忙しいんだね。」 「あ・・まぁ・・。ツアーが主やけど・・。」 「今日はわざわざ帰って来てくれたの?」 「いや・・こっちで仕事あって・・また明日から地方行く。」 「そっか。」 葵は少し寂しそうな顔をした。 「ありがとう。」 「え?」 突然お礼を言われ、亮は戸惑った。 「あたしのために・・こんなパーティー開いてくれて。」 「あ・・いや・・俺何もしてへんよ。龍二がさ、『俺ん家なら大丈夫やろ。』って言うてくれたんや。」 「そっか。でもありがとう。亮くんが居てくれて・・嬉しかった。」 そう言って笑顔になった葵を亮は思わず抱きしめた。 「え?亮・・くん・・?」 「・・好きや・・。」 「え?」 消えそうに呟いた声に、葵は驚いた。亮は葵の両肩を持って引き離し、葵を見つめた。 「俺・・葵のこと・・好きや・・。」 「え・・。」 突然の告白に葵は戸惑った。 「俺・・こんな気持ちになったん・・初めてなんや。だから・・どういう感情なんか・・よう分からんかった。でも・・今日葵に会って・・『ずっと一緒に居りたい』って・・そう思えた。・・これが『好き』って感情やって・・初めて・・気づいた。」 途切れ途切れにそう言って、亮はハッとした。 「あ・・ごめん。俺一方的で・・。」 葵は首を横に振った。 「ううん。嬉しい・・。」 「葵。」 亮はぎょっとした。葵の目に涙が溢れている。 「あたしもずっと亮くんのこと想ってた・・。けど・・どこかで一線を引いてた。亮くんは人気バンドのボーカルで、あたしはただの一般人だから・・。あたしなんかより・・もっとふさわしい人が居るんじゃないかって、ずっとそんな思いがどこかであった。でも・・いつの間にか・・亮くんの傍に居る時間が・・メールをしてる時間が・・あたしの中で一番大切な時間になってた。」 葵は涙を堪えながら必死で言葉を発した。 「あたしも・・あたしも亮くんのことが好きです。」 葵はそう言って笑顔を見せた。亮は再び葵を抱きしめた。 「・・よかった・・。」 ホッとした様子で亮は呟いた。 「やっとくっついたか。」 窓から様子を伺っていた慎吾が溜息を吐く。 「よう言うたな。亮も。」 武士は感心していた。『怖い』と言っていた亮は今はもういない。 「でもよかった。2人には幸せになって欲しいもん。」 美佳が2人を見つめながら言った。 「でもこれからが大変よ。恋人なら尚更今までよりも逢いたい感情が出てくるだろうし。メールだけでなんて無理でしょ?」 香織は現実的な問題を提示した。 「何とかなるって。」 龍二があっけらかんと言う。 「他人事だと思って・・。」 香織は頭を抱えた。 「俺たちやって何とかなったやん。」 龍二はそう言いながら香織が抱いていた龍哉を抱き上げた。香織は照れたのか、顔が赤くなっている。 「一番の問題はマスコミ対策やな。」 透は持っていたグラスに入っていたお酒を一気に飲んだ。 「一度目ぇつけられとるからなぁ。」 武士は伸びをしながら言った。 「それはやっぱりあたしたちが助けてあげなきゃでしょ。」 美佳はニッと笑った。 「せやな。」 「葵ちゃん、いい人たちに囲まれてるね。」 少し離れたところに居た直人は快人に話を振った。 「そだな。」 「大丈夫かな?」 「大丈夫だって。葵の周りには心強い味方がいっぱいいるし。それに・・。」 「それに?」 「父さんや母さんだって見守ってくれてるよ。」 「・・そうだね。」 翌日。一旦事務所に集まったメンバーはマネージャーの響を空き部屋に呼んだ。 「はぁ!?葵ちゃんに告白しただと!?」 「うん。」 「お前なぁ・・。」 響は脱力した。 「まだマスコミが嗅ぎ回ってるかもしれないんだぞ?」 「俺・・もう我慢なんてしたぁない。葵の傍にずっと居りたいだけや。」 亮の口からそんな台詞を聞くとは思っていなかった響は少し戸惑った。 「響さん。俺らがバレんように全力でバックアップすっからさ。」 「要はバレんかったらええんやろ?」 メンバーの言葉に、響は観念した。 「分かったよ。だけどこの事はちゃんと社長にも報告するし、今まで通り逢う事は制限するぞ。」 「分かってるって。」 何故か慎吾が答える。 「ったく。お前らは次から次へと・・。」 響は頭を抱えながら、部屋を出た。 「良かったな。亮。」 武士は亮の肩を組んだ。 「皆・・ありがと・・。」 亮のお礼の言葉にメンバーは妙に嬉しくなった。 「お礼なんて言わんでもええがな。」 「俺らはいつでもお前の味方やからな。」 「あぁ。ありがと。」 今までとほとんど変わらない亮と葵だったが、なるべく逢える様に努力した。それはもちろん周りの協力者のおかげだった。 龍二たちメンバーに紛れて双子を訪ねるフリをしたり、龍二宅に招かれてみたり。葵自身も親友に連れられて事務所に遊びに行くフリをしたり、事務所の人間になりすましてみたりした。逢える時間は限られていたが、2人はそれでもよかった。ほんの一瞬しか逢えない日もあったが、お互いの姿を確認するだけでも逢えないよりマシだった。 そして今日も事務所に待機していた葵と美佳だったが、忙しい亮は葵に気づいていながらも行ってしまった。 「また・・一瞬だけだったね。」 美佳が呟く。 「いいの。亮くんが忙しいのは分かってることだし。全く逢えなくなるより、全然いいよ。」 「葵・・。」 「それより・・ありがと。いつも付き合わせちゃって・・ごめんね。」 「何言ってるの。あたしにできるのは・・これぐらいしかないから・・。葵が気にすることないよ。あたしが好きでやってるんだから。」 「ありがとう。」 美佳は葵を抱きしめた。 「今日も一瞬だけやったな。」 武士がボソッと呟いた。 「・・うん。」 亮が頷く。 「元気出しや。今はしゃーないやん。」 武士は亮の肩を組んだ。 「分かっとる。」 分かっててもやり切れない。本当はもっと一緒の時間を過ごしたい。それが我侭だとしても、やっと気持ちを伝えられたと言うのに、この状況は悲しすぎる。 「ツアーが終われば、多少の時間はできるって。」 武士が慰めるように言う。確かに今はツアー中だが、これが終われば曲作りの時期に入る。そうすればきっと多少なりとも時間が空くだろう。今よりは。 「せやな。」 しかしあのポップな曲が話題となり、いつも以上に雑誌のインタビューやらテレビ番組、ラジオ番組の出演が多く入ってしまっていた。質問は決まって「どういう心境の変化ですか?」だった。 葵の存在が浮き彫りにならないように上手く誤魔化しながら、全てを切り抜けた。バレてはいけないとは言え、嘘を吐くのは亮にとって少し辛かった。せっかく素直になれたのに、嘘で塗り固められてしまいそうで、妙に不安だった。そんな時、葵からのメールが亮の不安を取っ払った。相変わらずな2人だったが、思いが通じ合ってると分かった現在、亮にとって素直に甘えられる存在だった。同時に葵を壊してしまわないようにとも気遣っていた。 逢えない日が続き、葵は気分が沈んでいた。しかし以前と違うのはやはり亮が言ってくれた「好きだ」と言う言葉に支えられてるからだと思う。単純かもしれないし、不安が全くないと言う訳ではないが、ただそれだけで前ほどの不安はなくなっていると思う。 「亮くんに逢えなくて寂しい?」 美佳に問われ、葵は苦笑しながら頷いた。 「そりゃね。でも忙しいのは毎度のことだし。仕方ないよ。」 諦めが入っているような口調に美佳は居たたまれなくなる。 「知ってた?『Love Letter』って曲、葵のこと想って書いたんだって。」 「え?そうなの?」 初耳だったらしい。 「やっぱり気づいてなかった?歌詞でバレバレじゃない。」 鈍いなぁと美佳が笑う。 「全然気づかなかった。」 「まぁ端から見て気づいたことだから、本人からしたら気づかないのかもねぇ。」 美佳は葵が入れてくれたコーヒーをすすった。葵は今更ながらに気づいて、少し顔が赤くなっている。 「あの曲は亮くんが葵のこと想ってくれてるって証拠だよ。」 美佳の言葉に嬉しくなったのか、笑顔が零れた。 「でも・・あたし・・何も返せないよ。」 しかし葵は突然不安そうな顔になる。 「何も要らないよ。ただ亮くんの傍に居てあげることが、最大のお返しだと思うよ。」 「傍に・・居てあげること?」 「そう。亮くんはきっとあたしらが想像する以上に心の闇を持ってると思うの。飽くまであたしがそう思っただけだけど。」 「心の・・闇・・。」 「今までそれをずっと1人で抱え込んでたんだと思うんだ。でも葵に逢って、それを少しずつ葵が知らない間に癒してあげてたと思うの。だからあの曲も歌えたんだと思う。」 今まで歌わなかったポップな曲調でも挑戦しようと思えたんだと、美佳は考えていた。 「だから葵が傍に居てあげることが、亮くんにとって何事にも変え難い大切なものだと思う。」 「美佳・・。」 「あー・・飽くまであたしが思ったことだけどね。」 「うん・・。でも本当にそうだとしたら、嬉しい。」 葵はそう言いながら微笑んだ。 久しぶりに2人がゆっくり逢えたのは、ツアーが終わった9月半ばだった。双子を訪ねてきたフリをしてメンバーと日向家に乗り込んできた。メンバーはリビングで飲み会をしている。もちろん香織も参加している。双子も参加しているか、もう自室に戻っているかもしれない。葵と亮は、葵の部屋にいた。2人は寄り添うように座っていた。 「やっと少しは落ち着いてきたのかな?仕事。」 葵が口火を切る。 「あぁ。ツアーも終わったし、これからは曲作り期間に入る。」 「そうなんだ。」 また沈黙が流れる。焦って話をしようという空気はない。 「あ、そう言えば、前に比べると歌い方変わってきたね。」 「そお?」 「うん。少なくとも喉を痛めそうな歌い方じゃなくなったきたよね?」 「あぁ・・まぁ・・曲調も変わってきたかんな。」 「そうだよね。曲調も優しくなったね。」 「葵の・・おかげかも・・。」 「え?」 「何でもない。」 亮は照れ隠しに話題を変えた。 「・・つけてくれてんや?」 亮は葵の胸元を指差した。葵は誕生日に亮が選んでプレゼントしたネックレスをしていた。 「うん。いっつもつけてるよ。すごく嬉しかったから。」 葵の笑顔に亮はドキッとした。でも喜んでくれているのが分かって亮も嬉しくなった。 「そういう亮くんもつけてくれてるじゃない。ピアス。」 葵は去年のクリスマスにプレゼントしたピアスを亮の耳に発見する。 「おう。」 照れているのか短く返事する。 「そう言えば・・今更だけど・・亮くんの誕生日っていつなの?」 「・・・。」 葵の質問に亮は戸惑った。 「どしたの?」 亮の様子がおかしいことに気づく。 「分からん・・。」 「え?」 「俺の本当の誕生日は、母親しか知らん・・。」 亮の言葉に葵はハッとした。亮は物心つく前に施設に預けられてるのだ。 「あ・・ごめん・・。」 「謝らんでええよ。俺の本当の誕生日は分からんけど12月ってことは覚えてるんや。」 「12月・・。」 「ほんの少しだけ・・断片的に残ってる記憶の中で、雪が降ってた。母親らしき女が『初雪』って呟いたのだけ覚えてる。」 亮は記憶を手繰り寄せるのが辛そうな顔でそう言った。 「そう・・なんだ・・。」 「そんな顔せんで。」 葵が目を伏せると、亮は苦笑した。 「俺が・・施設に預けられたのが12月24日やったから、それからその日が俺の誕生日になったんや。」 「クリスマス・イブ・・。」 葵が呟くと、亮が頷いた。 「あ、じゃあ去年あたしがロスに行った日?」 「そや。」 それが一番嬉しいプレゼントだった・・とは恥ずかしくて言えなかった。 「そうだったんだ。言ってくれたら良かったのに。」 「プレゼントももらえたしええかなーって・・。」 「そういう問題?」 葵が苦笑すると、亮は頷いた。 「そういう問題。」 「じゃあ今年はちゃんとお祝いしなきゃね?」 「ええよ。そんなん。」 「えー。だってあたししてもらってるのに・・。」 「葵は特別。」 「何でよ?」 「何でも。」 亮が意地悪く笑うと、葵はムーと膨れた。 「それに・・今年もレコーディングは海外かもしれんし。」 「あ、そっか・・。」 また逢えなくなってしまう。葵は先のことを考え、少し憂鬱になった。 「そんな顔せんで。早よ終わらせて帰ってくるから。」 「うん。」 今にも泣き出しそうな顔だった葵の頭を亮が優しく撫でる。亮はそのまま葵を抱き寄せた。 「うわ・・ええ感じちゃう?」 覗き見をしていた慎吾が小声で言う。 「ええなぁ。」 一緒に覗いていた武士が羨ましそうに言う。 「何がいいの?」 恐ろしい声が背後からしたので、2人はビクッとなった。 「うあ・・美佳ちゃ・・。」 「何やってんの?2人とも?」 にっこりと笑った顔が恐ろしい。震え上がった武士はその場で凍りつく。慎吾は音を立てないようにそっとドアを閉め、何事もなかったように立ち上がった。 「何もしてないよ?」 慎吾が笑顔であっけらかんと言い放つ。 「しらばっくれる気?」 美佳がギラッと睨む。危険を察知した武士と慎吾は一目散に逃げた。 「あ、こらぁ!!」 「美佳、どしたの?」 物音に気づいた葵が出てくる。 「な・・何でもない。邪魔してごめんねー。」 そう言うと美佳は武士たちを追って、下の階へ降りていった。 「変なの。」 葵は笑いながら、部屋に戻った。 「ったく。信じらんない。」 「何怒ってるの?美佳ちゃん。」 ビールを片手に香織が寄ってくる。 「この2人、葵の部屋覗いてたの!」 「あら。」 美佳が指差した先には、反省の意味で正座させられた慎吾と武士が居た。 「あんたたち進歩ないわねぇ。」 香織はグビッとビールを飲みながら平然と言う。 「で、どうだったの?」 香織は2人に迫った。 「香織さん!」 美佳は呆れながらも気になった。 「美佳ちゃんだって聞きたいんでしょ?」 「う・・。」 図星を突かれる。 「何やってん?」 龍二と透もやって来る。 「この2人が葵ちゃんの部屋覗いてたんだって。」 「ほぉ。」 香織の説明に龍二は2人を見下ろした。背が高く目つきが悪い龍二に見下ろされるととてつもなく怖い。 「で?どうなったんや?」 龍二は急に屈んで2人に聞いた。 「似たもの夫婦・・。」 美佳は脱力した。 「言うから足崩してもええ?」 武士は足が痺れてきたのか、先にお願いした。全員が美佳を見る。 「分かったわよ。いいよ。崩しても。」 全員に見られると、承諾しない訳にはいかない。 「で?どうだったの?」 香織が興味津々で聞く。2人は覗き見した一部始終を伝えた。 「何だ、いい感じなんじゃない。」 香織はホッと一安心したように言う。 「そいや今回のレコーディングってどこでやるん?」 まだ聞かされていない今後のスケジュールをリーダーである龍二に聞く。 「・・・。」 「何もったいぶってんの?言いなさいよ。」 黙りこくった龍二に香織が命令する。龍二は透と目で会話した。そしてようやく口を開く。 「実は・・ロンドンやねん。」 龍二の台詞に一同固まった。 「ろ・・んどん・・?」 武士が信じられないという風に呟く。龍二は「そうだ」と頷いた。 「ってどこ?」 お約束な武士のボケに一同コントのようにずっこけた。 「あのねぇ・・。」 香織は頭を抱えた。 「お前・・ロンドンぐらいどこにあるか知っとけ!」 龍二に怒られる。 「だって・・おいら勉強は得意ちゃうもーん。」 開き直った武士に一同溜息を漏らす。 「ロンドンはイギリスの首都でしょ。」 呆れながら美佳が教える。 「おぉ。イギリスか。」 「分かってんのかな・・。」 美佳は頭を抱えた。 「失敬な!イギリスぐらい分かるわ!」 「じゃあロンドンで分かってくれ。」 頼むように透に言われ、武士は言い返せなくなった。 「でも・・ロンドンってまた遠いな・・。」 慎吾が呟く。 「それなんよな・・。ただでさえなかなか逢えんのに・・余計逢えんようになる状況ってのは、なるべく作りたくなかったんやけどな・・。」 龍二は溜息を漏らした。 「あ。」 突然何かを思いついたかのように美佳が声を漏らす。 「どしたの?」 「一つだけある。2人を引き離さなくて済む方法。」 「え!?何々?」 興味津々でメンバーは体を乗り出した。 「あのね・・。」 美佳は思い付きを披露した。 「なるほど。それなら2人一緒に居られるってことか。」 「ええかもな。」 美佳の作戦にメンバーは乗ることにした。 |