
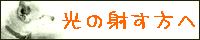



| font-size L M D S |
|
人間なんて大嫌いだ。自分勝手で、平気で裏切る。所詮人間なんてみな一緒だ。信じられるわけがない。 そう思ってた。あいつと出会うまでは・・・・・・。 俺は人間で言うところの【犬】という種類の生き物だ。犬の中でも種類が分けられてるらしいが、俺は混血なので雑種らしい。大きさは犬の中でも中くらいなので、中型犬と言われた。 俺は生まれた時から【野良犬】ってヤツで、今まで人の手を借りずに生きてきた。だから犬社会のルールも俺には染み付いている。その中でも俺の中で絶対的なルール。 『人間を信用するな』 これはいろんな 俺が初めて人間に接したのは、 俺は小さい時に母を亡くした。それも人間が運転する車という乗物に轢かれてだ。それでも俺は三匹の兄弟と共に、何とか暮らしていた。 そんなある日、人間のガキどもが、俺や兄弟を捕まえ、それぞれの家に連れて帰った。その瞬間、俺ら兄弟は一気にバラバラになってしまった。 それだけじゃない。俺を連れ帰ったガキは、親に怒られ俺を元いた場所に戻したのだ。だが、兄弟たちがいるはずもなく、それから俺は一人で生きていかなければならなくなってしまった。 その後も人間に連れ去られては、また置き去りにされた。何度同じ仕打ちを受けただろう? その度に俺は傷ついた。 「片耳が垂れてて、かわいくない」 「目が怖い」 「鼻ペチャ」 人間に懐かなかった俺は、そう罵られることも少なくなかった。 人間の一時的な感情のせいで俺は何度も酷い目に遭った。 だから決めたんだ。人間を信用しないって。 俺があいつと出会ったのは、初夏の心地よい風が吹いていた五月のこと。 その日も俺はいつも通り平凡な野良生活を送っていた。人間と極力関わらないように、なるべく人間がいなさそうな場所を歩いていた。 しかし、変な所に人間がいた。 「あれ? 犬だ」 向こうがキョトンとしている。俺だって驚いた。 若い青年がそこにいた。大学生くらいだろうか? 何でこんなところに人がいるんだ? ここは大人が通るには狭すぎる路地だ。路地と言うより建物と建物の間の隙間と言った方が正解かもしれない。人間のガキでさえ、こんな暗くて狭くてオバケでも出そうな場所を通ろうとはしないのに。 とにかく俺は見なかったことにして、クルリと方向転換をした。そのまま来た道を戻る。 「待って!」 青年が声をかけてきた。だがそんなの無視するに決まってる。 「待ってってば!」 青年は俺を引き留めようと、むんずと尻尾を掴んだ。咄嗟のことに俺は、牙を剥いて唸った。この路地が狭すぎて噛み付いたり、飛びついたりはできなかったのだ。 ヤツは一瞬怯み、俺の尻尾から即座に手を放したが、すぐにニコッと笑った。 「俺んち、来ない?」 またか。俺は呆れつつ、顔を背けた。 「無視すんなよ」 こいつ、頭おかしいんじゃないか? 俺以外にもたくさん犬はいるじゃないか。何で俺なんだ? 「なぁ、来るだけでもいいから来いよ。嫌なら逃げてもいいからさ」 何だ? やっぱこいつ頭おかしいのか? 俺はふとヤツの目を見た。 「な? 頼む」 そう言った目が、どこか寂しげだった。それに人間にお願いされたのは初めてだ。 何だか胸の奥がムズムズする。何だろう? このまま去ってもいいかもしれないが、何故か妙に気になる。 しゃーねーな。俺は仕方なくヤツに付いて行くことにした。 俺の気まぐれも困ったもんだ。何でこんな人間なんかを気になったんだろう? 今になって後悔し始める。 「ここが俺んちだ」 着いた先は、小さな一軒家だった。しかしヤツ以外に人間の姿が見えず、気配もない。 「入れよ」 急かされて家に入る。ヤツはどこからか雑巾を持ってきて、俺の足を丁寧に拭いてくれた。 「ここは俺一人だから、気兼ねしなくていいよ」 青年がそう言って笑う。一軒家に一人で住んでいるのか? 「おいで。風呂に入れてやるよ」 生まれて初めて風呂というものを体験したが、これは意外と気持ちがいいものなんだな。 「実は俺・・・・・・こないだ家族を事故で亡くしたんだ」 青年が俺の体をガシガシとこすりながらそう言った。 それで家にこいつ以外の人の気配がなかったのかと妙に納得する。 「だから・・・・・・ちょっとの間だけでいいから・・・・・・」 洗い終わったのか、お湯で泡を落とした。それまで俺の背後にいた青年が、俺の目の前にやってきた。 「しばらく俺といてくれないか?」 青年はすがるような目で俺を見た。人間にこんなにお願いされるのは初めてだ。 そうか。ヤツがほっとけないのは、俺と似てるからだ。 しゃーねぇな。少しだけ付き合ってやるか。 風呂場で一旦体を震わせて水滴を飛ばしたが、完全には乾かないので、青年がタオルで俺の体を丁寧に拭いてくれた。そうしながら青年は唸る。 「名前、何がいいかなぁ?」 名前とやらは、俺を拾ったガキが勝手につけたことがあるが、そんなのもうとっくの昔に忘れてしまった。 「耳が垂れてるからミミ!」 は? 「いや、センスがねーな」 すぐに訂正が入る。もしそんな変な名前になったら、俺は即行で逃げてやる。 「でも片耳だけ垂れてるのって珍しいよな」 またこいつもバカにするのか? 睨みを利かせるが、青年はそれに気づかず、俺の耳に優しく触れた。 「かわいいなぁ」 俺は驚いて思考回路が停止した。かわいいなんて、初めて言われた。 「ハッ。そうだ。名前・・・・・・」 青年はまたブツブツと考え始めた。 「お前の毛は、何だか不思議な色をしてるんだな」 タオルで拭きながら、俺の毛を見てそう呟いた。 「何かキラキラしてるから『アサヒ』ってのはどう?」 アサヒか。悪くないな。 「今日からお前はアサヒだ」 青年は俺をギュッと抱きしめた。初めてだった。 人間ってこんなに温かいものなのか? 「あ、そうそう。俺の名前は優一。よろしくな、アサヒ」 優一は俺の頭を優しく撫でた。 俺は一体何をやってるんだ? 人間なんて信用しちゃだめだ。そんなこと、分かり切ってるのに。 「父さん・・・・・・母さん・・・・・・」 隣で寝ている優一が呟く。その目に浮かぶ涙が、月明かりに照らされて光った。 しゃーねぇな。もうしばらく一緒にいてやるか。 次の日、優一は首輪と呼ばれる輪っかを手にやって来た。 「アサヒ。嫌かもしれないけど、首輪を付けよう」 飼い犬の証を付けておかなければ、保健所という場所に連れて行かれるらしい。そう言えばそんな人間にも追い回されたことがあったっけ。 「太陽の色だよ」 そう言って付けてくれた首輪の色は、オレンジだった。 リビングにはたくさんの写真が飾ってある。 それは古いものから最近のものまで、様々だった。必ずと言っていいほど写っているのが、恐らく優一なのだろう。そして時折一緒に写っている優一にそっくりな優しそうな男性が優一のお父さんで、おっとりした雰囲気の女性がお母さん。優一の隣に写っている優一より少し小さい男の子は、多分優一の弟だ。 「何見てんの? アサヒ」 台所で洗い物を済ませた優一が、俺に話しかけてきた。俺が写真を見ていると気づき、棚の上に置いてあった写真立てを一つ手に取る。 「これは、一ヶ月前の写真だ。俺の父さんは写真が好きで、よくこうして写真を撮ってたんだ」 優一はそう言いながら、写真を指でなぞった。少しだけ見えたその写真に写っていたのは、楽しそうに笑う優一と母親、そして弟だった。 優一を見上げると、その目に涙が溢れていた。家族を亡くしてからあまり経っていないのだ。無理もない。 優一はそっと写真立てを元の位置に戻すと、俺に向き直った。 「そうだ。アサヒも写真、撮ってやるよ」 そう言って無理やり笑った優一が、とても痛々しく見えた。 俺は他の犬とは違い、人間に懐くという行為をしなかった。それでも優一は変わらずに優しく接してくれた。 「アサヒは人間のこと、嫌いか?」 俺の体をブラッシングしていた優一が突然訊ねてきた。 犬である俺が答えるはずがないと分かっているのに、優一はよくこうして俺に話しかける。それはこの家に話し相手のいない優一がただ寂しいからかもしれない。 優一は俺の体を優しく撫でた。 「これは・・・・・・」 撫でていた手が止まる。あぁ、アレを見つけたのか。 「この傷、もしかして人間にやられたの?」 俺の体には数箇所の傷がある。それはもう随分昔からつい最近に至るまで、人間が俺に向かって投げつけた石のせいでできたものだ。 優一は更に他の傷も発見し、震えた。 「ごめんな。痛かっただろう? ごめん。ごめんな」 優一は涙ぐんだ声でそう呟いた。 何で優一が謝るんだ? この傷は優一がつけたものじゃないのに。 優一は俺をグッと抱きしめた。 「これじゃ、人間を嫌ってても仕方ないよな。でも、でもこんな人間ばっかりじゃないんだよ。だから・・・・・・人間を嫌いにならないで・・・・・・」 悲痛な叫びにも似た優一の言葉は、まるで優一自身を「嫌いにならないで」と言っているように聞こえた。 俺は人間が嫌いだ。信用だってしてない。 だけど、優一は・・・・・・嫌いじゃない。 しばらく優一と生活しているうちに、俺は優一を信用するようになった。優一は俺を裏切らない。なぜかそんな気がした。 優一は夜になるとよく電気も点けずに、縁側に座って月明かりを眺めていた。 時折泣き出しそうな優一の横顔を見ると、俺は何だか胸がざわついた。一気に家族を失った気持ちは、俺にはよく分かる。だけど、俺は言葉をかけることができない。 俺はそっと優一に寄り添って座った。 「アサヒ・・・・・・」 優一は驚いたように俺を見たが、優しく頭を撫でた。 「ありがとう」 その言葉が何だか妙に嬉しい。 俺たちは朝と夕方に散歩をすることにしている。その日も朝早く起きた優一が、リードを俺の首輪に付けた。 「さぁ、行こうか」 優一はリードを引き、俺は優一の隣を歩いた。 いつもの散歩道。人通りはまだ少ない。朝霧が視界を覆う。 俺はこの時間の散歩が好きだった。外界と切り離されたような空間に、俺と優一だけがいるような不思議な感覚になる。 「今日はちょっと霧が濃いな」 そう言いながら、優一はいつもより少しゆっくり歩いた。 その時、俺の耳に嫌な音が飛び込んできた。車のエンジン音だ。思わず立ち止まる。 「どうしたの? アサヒ」 急に立ち止まった俺に驚き、優一も立ち止まる。この音は俺にとっては嫌な思い出しかない。このせいで母を失ったんだから。 俺はいつもは垂れている片耳もピンッと張り、その音の方向を確かめた。近づいてくるエンジン音に俺の心臓が暴れだす。嫌な予感が、駆け巡る。 「アサヒ?」 一向に動こうとしない俺を、優一は怪訝そうな顔で覗き込む。 その時、俺の視界に猛スピードで優一に突っ込もうとしている車が見えた。 −−もう失いたくない。 俺は咄嗟に優一に飛びついた。 キキィーとすさまじいブレーキ音が遠くで聞こえた。目を開けるが、視界がぼやける。 あれ? 俺、車に轢かれたのかな? 「アサヒ! アサヒ、しっかりしろ!」 優一が必死に叫んでいるのが聞こえた。 そっか。優一は無事だったんだな。 「アサヒ! 大丈夫だよ! すぐ病院連れてってやるから!」 優一はそう言うと、俺を抱き上げた。 温かい優一の腕の中で、俺は優一と初めて会ったときのことを思い出した。 頭の中を駆け抜けたのは、温かくて、優しい思い出。 俺、このまま死ぬのかな? こんな人生だったけど、最期に優一に会えてよかったよ。 「アサヒ!」 名前を呼ばれ、目を開けると、優一が心配そうに覗き込んでいた。 「よかったー。もうダメかと思った」 そう言って、優一は胸を撫で下ろした。 あれ? 俺、死んだんじゃなかったのか? 「すぐ病院に連れて来られてよかったです。出血もそんなに酷くありませんでしたし」 獣医らしき男性が俺に包帯を巻きながらそう言った。 「ありがとう。アサヒ。俺を助けようとしてくれたんだろ?」 優一は俺の首に手を回して抱きしめた。温かい体温が伝わる。優一の優しい香りが鼻を駆ける。 「怪我も酷くないので、今日は帰ってもいいですよ。明日もう一度お越しください」 「はい」 獣医に帰宅許可をもらった優一は俺に向き直った。 「帰ろうか。アサヒ」 そう言って優一は俺を抱き上げ、怪我をしている部分を触らないように抱き直してくれた。 外に出ると、すっかり日は高く昇っていた。近づいてくる夏を予感させるような、真っ青な空だ。 優一の心臓の音が聞こえる。その優しい鼓動は、まるで母親といた時と同じような安心感をくれた。 「アサヒ。今度二人で朝日を見に行こう。キラキラして、すごく綺麗なんだ」 そう言った優一は、今まで見た中で一番優しい笑顔だった。 そうだな。優一。 いつか二人で見に行こう。俺の毛色と同じだと言ってくれたキラキラの朝日を。 |