
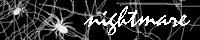



| font-size L M D S |
|
夢を見る。もう見ることはないと思っていた悪夢。 目の前で何度も惨殺される姉の姿。 止めようとしても間に合わない。すべてがスローモーションのようで、どんなに手を伸ばしても届かない。 やめろ!お願いだから!瑠璃を撃たないで!悪いのは僕なんだから!! 息苦しさに目を開ける。目に飛び込んできたのは、いつもの見慣れた天井だった。 「夢・・・。」 ここ数年見ていなかったのに・・どうして見るんだろう。鷹矢は布団から這い出て、冷たい水で顔を洗った。シンクを見つめ、しばらく呆然としていると、玄関でノック音が聞こえた。鷹矢は無造作に置いてあったタオルで荒く顔を拭き、玄関に向かった。扉を開けると、栗色の髪が見えた。 「おはよーって言っても、もうお昼過ぎてるけどねっ。」 明るく言いながら、バンドメンバーの譲が入ってくる。鷹矢はドアを広く開けた。 「どしたの?鷹矢、顔色悪いけど・・・大丈夫?」 「大丈夫・・。変な夢・・見ちゃって・・・。」 「変な夢?どんなの?」 「・・・覚えてない。」 鷹矢はまだ頭に残る残像を無理やり忘れようとした。狭い部屋の中に入る。 「ユズル、今日は早くない?迎えに来るん。」 譲はきょとんとした顔をした。 「何言ってんの?今日は響介のバースデーパーティーするから、早く集合するんでしょ?」 あぁ、そうか。そうだった。鷹矢はインディーズバンドのヴォーカリストだった。鷹矢を迎えに来た譲はキーボード。話題に出た響介はギタリストだった。他にリーダーでベーシストの哲哉、ドラムの遼平がいる。 「すぐジュンビする。」 鷹矢は服を着替え始めた。そんな鷹矢を譲はじっと見つめた。鷹矢は忘れていない。あの事件のこと。そう直感した。だけど鷹矢に何を言っていいかも、どうしたらいいのかも分からず、譲は黙っていた。 バンドの練習場になっている哲哉の家に着くと、既に遼平の車が来ているのが見えた。 この家に住んでいる哲哉は大企業の御曹司で、両親は今アメリカにいる。つまり日本のこの家には、哲哉しか住んでいない。それをいいことに広いこの家でいつもバンド練習をしているのだった。二人は車を降り、いつも通り家の中に入った。先に来ていた遼平たちはリビングで既に寛いでいた。 「いらっしゃい。」 家の主である哲哉が迎える。寛いでいたのは、哲哉、遼平、それに遼平の妹の遙、遙の幼馴染の篤季だ。篤季は鷹矢と親友でもある。 「鷹矢、顔色悪いけど大丈夫?」 いち早く遙が気づく。 「大丈夫。」 笑顔を無理やり作って答える。皆に心配かけたくない。 「そろそろ買出し行くかー。」 遼平が時計を見ながら立ち上がる。いつもパーティみたいなものだが、今日は特別なので主役である響介の好物を大量に作るらしい。彼は胃が宇宙じゃないかと思うほどたくさん食べるので、大量の料理を用意しなければならない。料理長の遼平が立ち上がると、哲哉と篤季に声をかける。 「二人、荷物持ちな。」 しょうがないなぁと言いながら、篤季と哲哉が立ち上がる。三人はぞろぞろと買出しに出かけた。それを見送った後、譲が立ち上がる。 「曲のアレンジしてくるから、地下室にいるね。」 地下室は練習場として使っている部屋だった。馬鹿みたいな広さの地下室は防音がしっかりなされているので、どんなに音を鳴らしても上にまで響いて来ないのだ。譲の次に立ち上がったのは遙だった。 「さて・・・下ごしらえでもしときますか。」 料理長遼平の妹である遙も料理の腕は確かだった。遼平がパーティの主食の材料を買いに行ったので、遙が作るのは恐らくデザートだろう。 「手伝うよ。」 「ありがとう。」 他愛のない話をしながら、デザートを作る。まずはメインのケーキ作りからだ。英語の方が話しやすい鷹矢は、英語が話せる遙とは英語で会話をしていた。もちろん日本語は目下勉強中である。 「・・ねぇ・・ハルカ。」 「ん?」 「死にたいって思ったことある?」 そう聞いて、鷹矢はハッとした。何を聞いてるんだろう。こんなこと聞いたりしたら、遙を困らせるだけだ。 「ごめん。今の・・忘れて。」 「あるよ。」 鷹矢の言葉にかぶるように遙が呟いた。 「え?」 「実際死のうとしたもの。」 まさかの返答に鷹矢は言葉を失った。鷹矢の様子を見ながらも、遙は続けた。 「あたし、中学の時に酷いイジメに遭ってたの。気づいた篤季や泉水が助けてくれたけど、三年の時、あたしだけクラスが違って、イジメはエスカレートした。でも・・それでもあたしは、何とか頑張ってた。どうしてあたしだけって言う思いは何処かであったけど・・。でもある時、あたしを庇って篤季が怪我をしたの。許せなかった。あたしを守ろうとして、篤季は怪我をした。これ以上あたしがこの世にいたら、きっと皆が傷つくって、そう思ったの。」 遙はそこまで一気に喋った。鷹矢を見て、曖昧に微笑んだ。 「じゃあ、あたしがいなくなればいいんだ。そうすれば、もう誰も傷つかない。そう考えると、妙に楽になったの。そしてあたしはその日手首を切った。」 遙はいつも左手首に巻いていたリストバンドを外し、傷を鷹矢に見せた。 「目を開けると、病院のベッドの上だった。意識が遠のいてる時、誰かに呼ばれた気がしたの。それは篤季の声だった。目を覚ました時、傍に居てくれたのも篤季だった。結局あたしはずっと篤季に助けられてたの。その時初めて自分は何て馬鹿なことしたんだろうって思った。」 遙はリストバンドを付け直した。 「あたしはもう一度生きようって思ったの。今度は逃げないで、守ってくれる人に頼りながらでも、生きていこうって。辛い事はたくさんあるけど、あたしの周りにはたくさんの人がいてくれるから、頑張ろうって思えるの。」 遙は優しく微笑んだ。知らなかった。遙と出会ったのは、その後だから、そんな過去があったなんて驚きだ。 「鷹矢は死にたいって思ったことあるの?」 今度は遙に質問される。鷹矢はしばらくの沈黙の後、口を開いた。 「あるよ。いつも思ってる。」 鷹矢の呟きに遙は驚いていた。鷹矢は少しずつ悪夢を口にした。 「俺がまだアメリカでルリ・・姉さんと住んでた14の時、ドラッグを売るって言うバイトをしたんだ。」 何となくだがその話は聞いたことがあった。 「金が欲しくて・・。両親は事故で亡くなってて、歳の離れたルリが俺を育ててくれてた。そんなルリにちょっとでも楽させてやりたくて・・。俺は1回きりっていう約束でドラッグを売ったんだ。もちろん、その時はドラッグなんて知らなかった。リストを渡されて、これを売れって。その仕事が終わって、報酬をもらった帰り道、ルリに会って、一緒に帰ってた。そしたらイキナリ目の前に銃を持った男が現れたんだ。俺の口を封じるために、俺を殺そうとした。その男は怖くなって動けないでいる俺を狙って撃った。もうだめだって思ったとき、目の前にルリが飛び込んできた。」 そこまで話して、鷹矢は深呼吸した。呼吸を整えながら、続きを口にする。 「俺の代わりにルリが撃たれたんだ。俺を殺そうとしていた奴らはもう一度俺に狙いを定めた。だけど銃声を聞いた通行人たちが騒ぎ始めて・・。結局奴らは俺を殺さずに逃げた。ルリは誰かが呼んだ救急車で運ばれて、病院で治療を受けた。けど・・その甲斐もなくそこで亡くなったんだ。」 鷹矢は涙が溢れていた。遙は鷹矢の頬に触れた。 「自分を責めてるの?」 遙の問いに、ゆっくりと頷く。 「夢を・・見るんだ。何度も俺の目の前で、ルリが殺される夢。・・もう見ないって思ってたのに・・。」 遙は鷹矢を落ち着けようと、リビングの方のソファに座らせた。 「ユズルのお父さんに引き取られて、日本に来てからも何度も見た。けど・・セリカに会って、安心したんだ。ルリが生きていた頃のようで・・。」 芹華とは篤季の姉で、哲哉の恋人でもある女性だ。不安がっていた鷹矢に姉代わりになってあげると言って、実の弟のように可愛がった。その芹華は今は上京し、モデルとして活躍している。 「芹華姉が、鷹矢の精神安定剤だったんだね。」 遙は呟き、ソファに座っている鷹矢の頬を両手でそっと包んだ。 「ねぇ、鷹矢。一人じゃ・・ないからね?あたしや篤季、お兄ちゃん達だって、鷹矢のこと大切に想ってる。芹華姉だって、そうだよ?あたし・・たまにモデルの仕事で芹華姉に会うけど、第一声はいつも『鷹矢元気?』なんだよ?」 それを聞いて、鷹矢は胸が熱くなった。 「皆、皆鷹矢のこと想ってる。だから辛い時は皆に頼ればいい。それに・・鷹矢にも居るよ。あたしに篤季が居てくれたように、鷹矢にもそんな存在がきっと・・・。」 「ありがと。」 鷹矢は遙をぎゅっと抱きしめた。遙の言葉にほんの少し勇気をもらった気がした。 その日のパーティは何事もなく無事に終わった。 何気なく過ごしている生活の中でも、やはり悪夢を見続けていた。息苦しさで目覚める毎日は、鷹矢を精神的に追い詰めて居た。いつしか一番大好きな歌うことでさえ、疲れを感じるようになっていた。溜息ばかりの毎日。遙はああ言ってくれたけど、本当は世界にたった一人なんじゃないかと思う。夜の闇が全てを覆って、何もかも終わってしまえばいいのに。いつしかそんな事を考えていた。 『自分を責めてるの?』 いつか問われた遙の質問がふと頭に浮かんだ。責めるしかないじゃないか。俺のせいで瑠璃は死んだんだ。俺があんな馬鹿なことをしなければ、命を狙われることなんてなかった。瑠璃だって死ぬことなかった。いっそこの夜の闇に吸い込まれて、消え去ってしまいたい。瑠璃の代わりに俺が死ねばよかった。鷹矢は何度も自分を責めた。 「何や、ここにおったんか。」 ふと声がして、鷹矢は現実世界に引き戻された。顔を上げると、哲哉が立っていた。 「急に姿が見えんくなったから、どこ行ったんかと思った。」 哲哉は鷹矢の隣に座った。いつもなら深夜はコンビニでバイトをしているのだが、今日はバイトが入ってなかったので、そのまま哲哉の家に居座っていた。楽しくお酒を飲んでいる皆の邪魔をしないように、鷹矢はそっと抜け出して外に出てきたのだった。 「皆は?」 「響介は酔いつぶれたけど、遼平と譲はまだ酒飲みながらゲームやってる。」 「そう。」 目に浮かぶ光景にほんの少し笑みが漏れる。 「鷹矢、大丈夫か?」 ふと声をかけられ、鷹矢はきょとんとした。 「え?」 「最近、全然元気ないやろ?」 やっぱりバレてたか。鷹矢は観念したように溜息を吐いた。 「俺・・またあの夢を見るようになったんだ・・。」 零れた言葉は英語だった。日本語より英語の方が伝えやすい。哲哉もまた英語ができる人の一人なので、気兼ねなく英語で話せる。 「あの・・・悪夢を?」 事情を知っている哲哉がそう問うと、鷹矢はコクンと頷いた。 「もう見ることないって思ってたのに・・。最近毎晩のように見るんだ。」 「・・・芹華が居なくなってから?」 的を射た質問に鷹矢は驚きながらも、曖昧に頷いた。哲哉は自分の恋人である芹華が自分以上に鷹矢の精神安定剤であることを知っていた。鷹矢は彼女を姉と慕い、いつも傍に居た。芹華の傍に居る時は、鷹矢も哲哉も不思議なくらい安心できた。でもいつまでも芹華に甘えてばかりじゃダメだって、鷹矢自身気づいていた。 「セリカが上京して・・しばらくは何とかがんばろうって思ってた。早く認めてもらえるようになりたいって・・。だけど・・それもいつの間にか崩れてきた。どうすればいいか・・全然分からない・・。」 鷹矢は頭を抱えてうずくまった。哲哉は鷹矢の頭を優しく撫でた。 「俺もあるよ。そういう時。」 哲哉の思わぬ言葉に、鷹矢は顔を上げた。 「芹華は俺にとっても精神安定剤みたいな存在なんだ。上京する時、正直引き止めたかった。でもそれは俺の我侭で、芹華には芹華の夢があるんだって、そう思った。それでも芹華が居なくなった後の数ヶ月間は、抜け殻みたいに過ごしてた。この世にたった一人取り残されたみたいな気持ちになった。」 哲哉の言葉は今の鷹矢の現状にシンクロしていた。 「俺は・・小さい時から孤独だった。周りに人がたくさん居ても、自分の味方は誰もいないような気がして・・。でも芹華に出会って、一人じゃないって思えた。芹華だけじゃなく、俺の周りには遼平や響介や譲や鷹矢がいてくれた。芹華がいなくなって確かにまた孤独を感じたけど、皆が居てくれたから俺は頑張ろうって思えた。早く認めてもらってまた芹華の傍にいたいって。」 哲哉は鷹矢に優しく微笑みかけた。 「誰も一人じゃ生きていけない。そこまで皆強くない。けど・・一人じゃないんだよ。自分が気づいてないだけで、周りには常に自分を支えてくれる誰かって言う存在がいるんだ。毎日食べるお米や野菜を作ってる農家の人、鷹矢が今着ているような服を作ってる人・・。見ず知らずの誰かが、今の鷹矢を支えてる。世界には星の数ほど人がたくさんいて、それでも俺らはこうして出会った。それって、物凄い確率の奇跡だと思わん?」 哲哉の問いに、コクンと頷く。 「瑠璃だってそうだよ。瑠璃はあの時身を挺して鷹矢を助けたこと、誇りに思ってるんじゃないかな?」 「そ・・かな・・。」 半信半疑で答える。 「鷹矢にとって瑠璃がたった一人の大切な家族だったように、瑠璃だって鷹矢のことをたった一人の大切な弟だって思ってたに違いないよ。鷹矢が瑠璃の立場なら、きっと同じことしたろ?」 そう聞かれ、鷹矢は頷いた。確かに自分が瑠璃の立場なら、身を挺して守ったかもしれない。例え命を落とすと分かっていても。 「瑠璃のおかげで、今鷹矢はこうして生きてる。確かに・・瑠璃が亡くなったことは本当に悔やむべきことだし、自分を責める気持ちも分かるよ。でも・・過去は変えられない。」 哲哉の言葉が胸に沁みた。分かってたよ。過去は戻せないって。取り返しのつかないことを、俺はしたんだ。 「もし瑠璃が生きてたとしたなら、鷹矢はどんな自分を瑠璃に見てもらいたい?」 鷹矢はしばし考えた。どんな自分になりたい?どんな自分で瑠璃に会いたい? 「瑠璃は・・・俺が歌ってる時の顔が一番好きだって言ってくれた。俺の歌を・・嬉しそうに聞いてくれた。」 鷹矢は思い出し、思わず涙が溢れた。堪えながら続ける。 「俺は・・ヴォーカリストとして認められたい。ルリが望んだように・・。」 鷹矢は夜空を見上げた。満天の星空だった。ヴォーカリストとして生きることを決めた、瑠璃がまだ生きていたあの日も、満天の星空だった。哲哉は鷹矢の頭をガシガシと撫でた。 「頑張ろうな。」 哲哉の言葉に、鷹矢は笑顔で頷いた。 あれから毎日見ていた悪夢は見なくなった。精神不安定になると見てしまう時もある。だけど以前よりも少しだけ強くなった気がする。 瑠璃と見たヴォーカリストとしての夢を絶対に叶えてみせる。 鷹矢はそう誓ったあの日の星空を思い出しながら、夢への新たな第一歩を踏み出した。 |